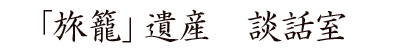
[ホームへもどる] [新規投稿] [新規順タイトル表示] [ツリー表示] [新着順記事] [留意事項] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]
|
|
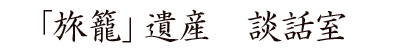
|
|
るびーさん、こんにちは。
>確かに正面から見て左半分は鉄筋の部分がありますが、そんなに違和感は感じられませんでした。
そうですか。写真だけではほんのちょっとの部分しか分かりませんね。
> 是非とも泊まってみる必要がありそうですね。
ええ。一階には泊まる部屋はないような気がしました。たしか…
> フォーラム時に私がご紹介しました「旅籠」、これらはいずれも実際に泊まっていないので載せようかどうか迷っています。
あまり深くお考えにならなくても、気分でどうぞ(^^;。徳森はぜひお願いします。あの写真は何度で見たくなるものだと思います。
ほりうちさん、こんばんは。
るびー です。
> おそまきながら「中国」に芳和荘の枝を作りましたので、そちらにコメントいただければ幸いです。
気づくのが遅れて失礼しました。
> 私も芳和荘を見つけるまでは、中村旅館がいいかなと思っていました。一部鉄筋化しているような感じなのでしょうかね。部分的に小田原の古清水みたいな雰囲気になってるのかなと…。
確かに正面から見て左半分は鉄筋の部分がありますが、そんなに違和感は感じられませんでした。
> > しかし、芳和荘、いったい幾つの部屋があったのでしょうね。
>
> 道路側から見て、玄関の上は中庭に面していない部屋が並んでいます。そして玄関から見て、右側の列と左側の列ですね。中庭部分が五間としましたから、一間(ひとま)間口二間見当として三間ていどでしょうかね。そんなに部屋数が多いわけでもないかもしれません。ちなみに一階がどうなっているか、すっかり忘れてしまいました(^^;
是非とも泊まってみる必要がありそうですね。
さて、記事を増やすべく、東海に星出館を載せましたが、フォーラム時の内容の丸写しです。
フォーラム時に私がご紹介しました「旅籠」、これらはいずれも実際に泊まっていないので載せようかどうか迷っています。
るびーさん、こんにちは。
伊勢は「さすが」という感じですね。私がネット上で捜したの範囲でも、良さそうな雰囲気の旅館がいくつかありました。星出館の他に「紅葉軒」「山田館」「柏屋」ですか。あと、一度は見てみたい「麻吉」。
伊勢関連は伊勢市街地にとどまらず、各地へ伸びる伊勢街道沿いにもいろいろありそうです。
松阪の鯛屋ももちろんそうですし、広くは彦根の鳥羽やもその仲間と言っていいのでしょう。相可には「鹿水亭」というのがあるみたいで、ここもちょっとチェックに行きたいところです。
> この建物、正面から見ても入り組んでいて平面的な造作ではありませんが、内部も複雑な造りです。中庭を囲んで二階にぐるっと一周できる回廊があり、その一部には木の橋がかかっていて非常に凝っています。
う〜ん、これは泊まってじっくり見てみたいですね。
> 外観も含めて伝統的な雰囲気の「旅館」で、外人用の情報誌にも紹介されているらしく、私が泊まったときも多くの外人が泊まっていました。
これも伊勢ならではといえるかもしれません。「旅籠」遺産に紹介しているようなところは、どこも外国人に教えてあげたいと思うのですが、サポートがないと宿の方で困っちゃうところが多そうで…。日本人より外国人が喜びそうな内容ではあるんですが。さて、どうしたものかな(^^;。
るびーさん、こんにちは。
おそまきながら「中国」に芳和荘の枝を作りましたので、そちらにコメントいただければ幸いです。
> 橋が架かっているのですね。わたる人もいないようなので安心して猫がくつろいでいますね。
すいません、この橋は芳和荘への橋ではございません(^^;。芳和荘の前の道と川の間に、一列住宅が建ち並んでしまいましたので、芳和荘は川には面していない状態になりました。
萩は河口の三角州に出来た町ですから、水で行き来するところは多かったでしょうね。
> 芳和荘の近くにあった萩最後の銭湯だった三光湯もこんな木の橋を渡って行ったような気がしました。
銭湯もどんどん無くなってしまいますねぇ…。もったいない。
> ちなみに私が萩に行ったときは、確かまだ楽天トラベルに芳和荘が登録されていないときでしたので、玄関の脇に帳場ある典型的な和風旅館の中村旅館に泊まりました。まあ、昔ながらのと言った感じでした。
私も芳和荘を見つけるまでは、中村旅館がいいかなと思っていました。一部鉄筋化しているような感じなのでしょうかね。部分的に小田原の古清水みたいな雰囲気になってるのかなと…。
> しかし、芳和荘、いったい幾つの部屋があったのでしょうね。
道路側から見て、玄関の上は中庭に面していない部屋が並んでいます。そして玄関から見て、右側の列と左側の列ですね。中庭部分が五間としましたから、一間(ひとま)間口二間見当として三間ていどでしょうかね。そんなに部屋数が多いわけでもないかもしれません。ちなみに一階がどうなっているか、すっかり忘れてしまいました(^^;
ほりうちさん、おはようございます。
るびー です。
橋が架かっているのですね。わたる人もいないようなので安心して猫がくつろいでいますね。
芳和荘の近くにあった萩最後の銭湯だった三光湯もこんな木の橋を渡って行ったような気がしました。まあ、私が行ったときは、すでにこの三光湯も廃業していいましたが。
ちなみに私が萩に行ったときは、確かまだ楽天トラベルに芳和荘が登録されていないときでしたので、玄関の脇に帳場ある典型的な和風旅館の中村旅館に泊まりました。まあ、昔ながらのと言った感じでした。
しかし、芳和荘、いったい幾つの部屋があったのでしょうね。もちろん、今現在はある部屋全てを使っていないと推測されますが。(大きな古い旅館なんかはそういう傾向が強いようですね)
遊郭として使っていたときは本当に華やかで賑やかだったのでしょうね。
ではまた
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |